長期インターンは意味ない?よくある5つの誤解と本当のメリット
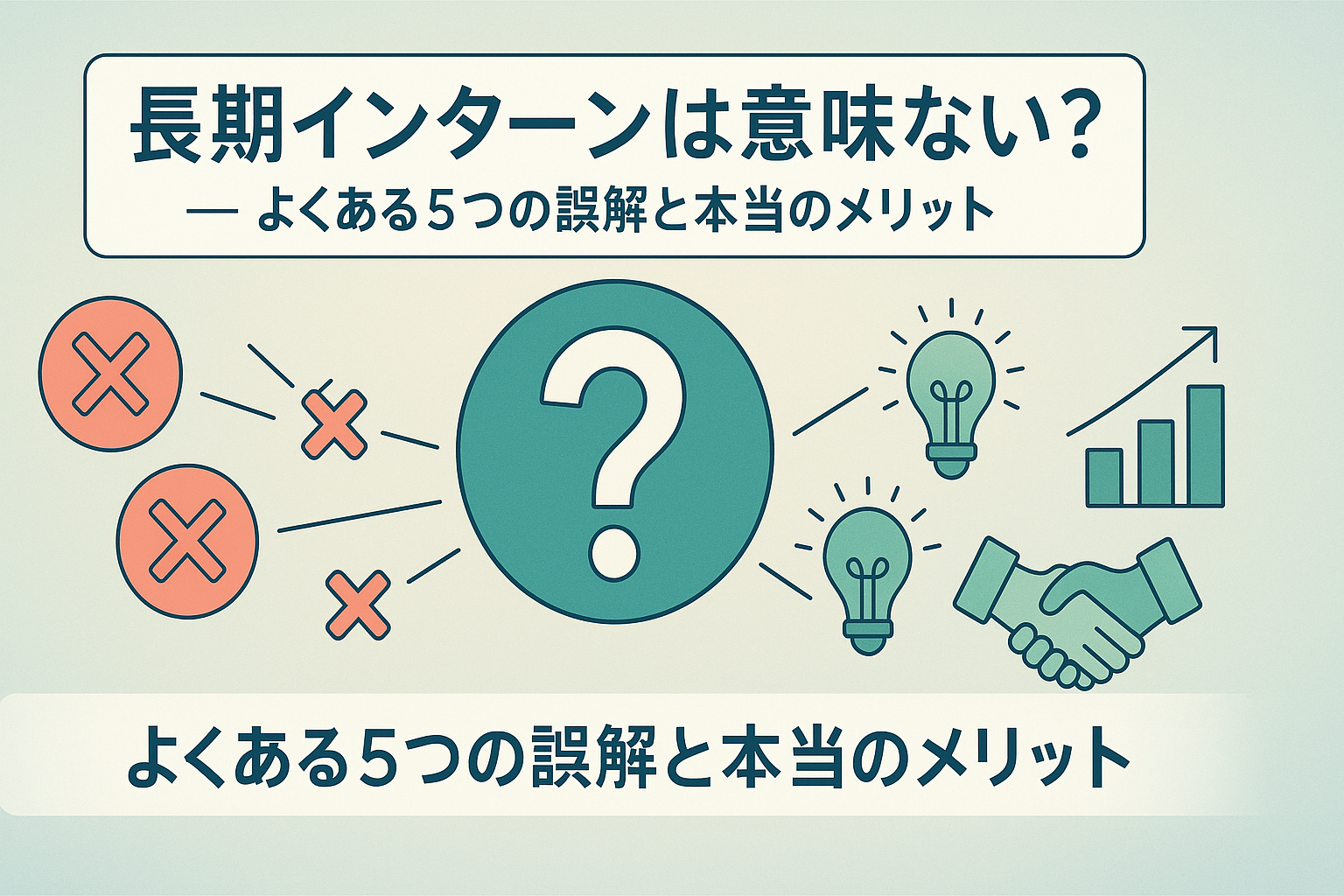
「長期インターンは意味ないのでは?」そんな不安を抱えていませんか。大学の授業や部活・アルバイトに集中すべきで、インターンシップに時間を割く価値が本当にあるのか悩む学生も多いでしょう。しかし、結論から言えば長期インターンは取り組み方次第で大きな価値をもたらします。本記事では、長期インターンをめぐる5つの「意味ない」という誤解をデータと体験談から検証し、真のメリットを解説します。最後には失敗しないインターン先の選び方チェックリストと、厳選求人への一歩を紹介します。
この記事を読めば、長期インターンの実態を正しく理解し、あなたにとって最適な行動を決められるでしょう。それでは見ていきましょう。
長期インターンとは?定義と一般的な期間・報酬
長期インターンシップとは、一般的に3か月以上にわたり企業で定期的に実務を体験する制度を指します。週2~3日、1日4~8時間程度を授業と並行して働く形態が一般的です。2024年以降、国のガイドラインでは5日以上(専門的プログラムは2週間以上)のプログラムだけが「インターンシップ」と呼べるよう定義されました。短期インターン(1日~1週間程度の職業体験)との主な違いは以下の通りです。
◇参加対象
短期は就活直前の学生向けが多いのに対し、長期インターンは大学1年生から大学院生まで幅広く参加できます。ただし公式には学部3年生以上を対象とするのが望ましいとされています。
◇期間
短期は数日~数週間の集中型、長期は1か月以上で中長期的に継続します。
◇報酬
短期インターンの多くは無給(交通費支給程度)ですが、長期インターンの主流は有給です。時給相場は約1,000~1,500円程度で、IT企業やベンチャーでは1,500円以上の高時給案件も見られます。地域の最低賃金レベルからスタートし、成果に応じてインセンティブが出るケースもあります。
◇内容
短期は会社説明会やグループワークなど職場体験的な内容が中心。一方、長期は実際のプロジェクトや業務を任されます。マーケティング、エンジニアリング、営業支援など専門性の高い仕事に携わり、単なる見学ではない実践経験を積めるのが特徴です。
こうした長期インターンは近年増加傾向にあります。例えば、長期インターン求人サイトでは1万名以上の学生ユーザーが活用する規模に拡大しています。とはいえ実態として、長期(2か月以上)インターン参加者は学生全体のわずか2~3%程度に留まります。一方で1日型の短期インターン参加率は70%前後にも達し、ほとんどの学生が何らかのインターンを経験している状況です。つまり、「長期インターンに挑戦した学生」は少数派だからこそ就活で差別化できる存在とも言えます。
また、有給か無給かは重要なポイントです。長期インターンは法律上「労働者」とみなされ、通常は給与(時給または成果報酬)が発生します。最近では有給インターンが主流になりつつあり、無給の募集は減ってきています。実際にインターン情報サイト「Infra」に掲載されている有給長期インターン求人の平均時給は1,400円超とのデータもあります。報酬面だけでインターン先を選ぶのはおすすめしませんが、無給と有給で迷ったら基本的に有給インターンを選ぶ方が良いでしょう。お金をもらう責任感も成長の糧になります。
期間に関して言えば、参加期間の平均は半年~1年程度が多い傾向です。週2日ペースでも半年続ければ実質40~50日間働く計算となり、それだけでも相当の経験値になります。中には1年以上継続して企業の戦力級になっている学生インターンも存在します。実際、ある企業では1年以上続けて働くインターン生もいて非常に助かっていると語っています。
まとめると、長期インターンは「大学に通いながら週数日、有給で実務経験を積む場」です。短期との違いを踏まえ、自分の目指すキャリアや学業との両立を考慮して、参加を検討すると良いでしょう。
長期インターンは意味ない?と言われる5つの理由と実際のデータ
長期インターンに興味はあるものの、「意味ない」「やめとけ」といった声を耳にして二の足を踏んでいませんか。ここでは、巷で言われる「長期インターンは無駄」論の主な5つの理由を取り上げ、その誤解をデータや事例で払拭します。「意味ないのでは?」という疑念を正面から解消し、自信をもって一歩踏み出せるようにしましょう。
◇学業との両立が難しい
よくある声:「授業や試験があるのに長期インターンなんて両立できない」
確かに、長期インターンの参加率が低い一因は学業との両立の難しさにあります。実際、就職白書2024のデータでも2か月以上のインターン参加者はわずか2.2%と少数派で、長期インターンの参加率が低い理由の一つに「学業との兼ね合い」が挙げられています。週5日フルタイムで働くとなれば授業に出られず本末転倒でしょう。
実際には:しかし、工夫次第で学業とインターンの両立は十分可能です。実際には週2~3日・1日4~6時間程度の勤務体系を選ぶ学生が多く、試験前は勤務時間を調整できる企業も少なくありません。長期インターン先の多くは「学生の本分は学業」と理解しており、柔軟に対応してくれます。例えば「テスト期間中は週ゼロでもOK」「長期休暇中にまとめてシフトに入る」といった調整も可能です。リモート勤務可の企業なら通学時間を省ける分、スキマ時間で働くこともできます。
成長視点:むしろ限られた時間で両立を図ることで時間管理能力が向上するメリットもあります。社会人になれば仕事とプライベートの両立は必須スキルですから、学生のうちにその訓練ができるのは大きな強みです。履修登録を工夫して授業を集中させたり、休学せず長期インターンに参加している学生も多数います。また文部科学省や大学もインターンシップ推進の中で「学業との両立」を重視しており、単位認定されるインターンプログラムも増えてきました。
結論として、「学業優先」は大前提ですが、長期インターン=学業がおろそかになるとは限りません。計画的に時間配分し企業とも相談すれば、多くの学生が両立に成功しています。不安な場合はまず週1~2日の少ない日数から始めてみると良いでしょう。「授業もバイトも両立した経験」は就活時の自己PRにもなります。両立の難しさばかり心配せず、時間術も含めた成長の機会と捉えてみてください。
◇雑用ばかりでスキルがつかない
よくある声:「インターンでは結局、コピー取りやお茶くみなど雑用しか任されず、時間の無駄になる」
SNSや就活掲示板でも「名刺の整理や単純作業ばかりだった」「インターン生だからといって思考や提案を求められない仕事ばかり…」といった不満の声は根強くあります。確かに、教育体制が整っていない企業だとインターン生を安価な雑用係のように扱うケースも皆無ではありません。そうした環境ではモチベーションが下がり、「やっぱり意味なかった」と感じてしまうかもしれません。
実際には:しかし現在は、多くの企業がインターン生にも実践的な業務を任せる傾向にあります。長期インターンではマーケティング施策の企画・運用や、エンジニアリング業務の一部、営業リストの作成から実際の顧客提案まで担当する例もあります。つまり「インターン=雑用」という図式は古い誤解です。実際に「単なる作業者ではなく、責任ある仕事を任せてもらえた」という体験談も多く、普通のアルバイトでは得られないやりがいを感じる学生が増えています。例えば、とある長期インターン生は「企業の法務リスクチェックや顧客提案を任され、自分の提案が売上やリスク低減に直結する責任ある仕事だった」と語っています。雑用だけでは得られない知識や提案力が身に付いた良い例です。
改善策:もしインターンを始めて「雑用ばかり…」と感じたら、自分から積極的に仕事を取りに行く姿勢も大切です。「○○をやってみたい」「資料作成を手伝わせてほしい」など主体性を示せば、徐々に大きな仕事も任せてもらえるでしょう(「仕事の報酬は仕事」という言葉通りです)。長期インターンは目的次第で意味あるものにも無意味な時間にもなり得ます。逆に受け身で指示待ちだと、「マニュアル通りにこなすだけ」で終わってしまい、アルバイトと変わりありません。そうならないために、目標意識を持って主体的に動くことが重要です。
要するに、「雑用ばかり」というのはインターン先の質または自分の姿勢の問題であり、長期インターンそのものの価値を否定する理由にはなりません。専門スキルや実務経験が積める良質なインターン先を選び(選び方は後述のチェックリスト参照)、自ら機会を掴みにいけば、必ずや得られるものがあります。「雑用しか任されないインターン」を避け、「成長できるインターン」を選ぶ目を養いましょう。
◇就活評価に直結しないと言う声
よくある声:「長期インターンやっても就活で有利にならないって聞いた」「実際インターンしたのに内定に繋がらなかったから意味がなかった」
就職活動においてインターン経験の評価を不安視する声もあります。「インターンより学業成績や資格の方が重視される」「結局インターンに行かなくても内定はもらえる」などの意見ですね。確かに、インターン参加=自動的に内定ではありませんし、参加しなくても他の方法で十分アピールできる場合もあります。
実際には:しかし統計を見ると、長期インターン経験者は就活で明確に有利です。経済産業省の調査によれば、インターンシップ経験者の内定率は未経験者より約1.2倍高いという結果が出ています。また、特にベンチャー企業では長期インターンを経てそのまま正社員採用されるケースが増えています。リクルートキャリアの調査でも、長期インターン先に就職した学生の定着率(離職せず働き続ける割合)が一般採用より高い傾向が報告されています。これらのデータは、長期インターンが就職活動やキャリアにプラスに働いていることを示しています。
さらに人事担当者の声として、「長期インターンの経験は学生時代に力を入れたこと(ガクチカ)として非常に評価される」ことが多いです。ポイントは単に「参加した」ではなく、「その中で何を学び、どう成長したか」を語れるかどうか。長期インターンは実務に深く関わるぶん具体的な成果やエピソードを示しやすく、論理的に課題解決プロセスを語れるため、強力なアピール材料になります。事実、多くの採用担当者は長期インターンでの経験がある学生に注目し、「実践力があり主体的に動ける人材だ」という評価をしています。面接でも「インターンで学んだことを教えてください」など質問される場面が増えており、そこで明確な成果を語れれば他の学生と差別化できるでしょう。
考え方:「長期インターン=就活直結の内定パス」ではありませんが、就活準備の一環として非常に有益です。仮にインターン先から直接内定が出なくても、得たスキルや知見、人脈は他社の選考でも必ず活きます。インターンを通じて業界・企業研究が深まったり、自分の適性を把握できれば、エントリーシートや面接での志望動機にも厚みが出ます。要はインターンを「学びの場」として最大限活用し、その成果を就活でアピールすることが大切なのです。
実際、「インターンに参加したが内定がもらえず無駄だった」という極端な声は、インターンの本来の目的である“学び”よりも“就活の手段”としての側面だけで評価した結果生まれていると言えます。就活のゴールは内定獲得ですが、その先のキャリアでも成長し続けることが大事です。長期インターンで培った実務経験や人間力は、入社後もあなたの武器になります。就活だけをゴールにせず、その先のキャリアまで見据えて長期インターンを活用すれば「意味しかなかった!」と言える成果が得られるでしょう。
◇ブラック労働のリスク
よくある声:「長期インターンはブラック労働させられるって聞いたけど…」「無給でこき使われて授業も出られない最悪の体験談を見た」
確かに、「ブラックインターン」と呼ばれる悪質なケースが存在するのも事実です。Twitter上でも「学生をこき使い消耗させるだけ、中身がなくキャリア形成にならないインターンが多い」との告発が見られます。例えば、ある学生の彼氏は地方から都内企業のインターンに1か月半参加したものの、住居は用意されたが交通費は自腹、給料0円で社員同様の長時間労働を課されたといいます。昼夜の弁当支給こそあれど、まさに「ブラックインターンにも程がある」待遇です。他にも「無給なのに夜0時まで働かされた」「10時間働いて日給3,000円(歩合制)」等々、耳を疑うような事例が報告されています。こうした体験をした学生が「インターンなんてやめとけ」と感じるのは無理もありません。
実際には:しかし、それは一部の悪質なケースであって、大半の長期インターンは適切な条件と配慮のもと行われています。繰り返しになりますが、本来長期インターンは有給であり、社員と同様の実務を行う以上きちんと労働の対価をもらうべきものです。厚生労働省も「インターンシップと称して労働させ対価を払わないのは労働基準法違反の可能性がある」と注意喚起しています(参考:厚労省インターンシップ留意点)。実際、「無給の長期インターンはやめましょう。成果と対等にお金をもらう経験も大切」というアドバイスもあります。報酬の有無は企業側の姿勢を測る指標の一つです。有給だから必ず良い環境とも限りませんが、無給の場合は「なぜ無給なのか」「本当に学びがあるのか」を慎重に見極める必要があります。
対策:ブラックなインターンを避けるために、以下のポイントに注意してください。募集要項で業務内容や待遇が不明瞭な企業は要注意です。「成長できる!」と煽る一方で具体的な仕事内容を書いていなかったり、やたら高圧的な面接をするような会社は避けましょう。また、契約内容を確認し、労働条件通知書やNDA(秘密保持契約)を交わすかどうかもチェックポイントです。しっかりした企業ほどインターン生にも契約書を交わし、守秘義務などを確認します。逆に口頭であいまいな指示しかなく契約書も無いような場合はリスクがあります。
幸い、最近では学生がブラックな募集を見抜けるよう情報交換するコミュニティも発達しています。就活サイトの口コミや先輩の体験談を調べ、怪しい企業は避けましょう。万一参加して「これはおかしい」と思ったら、大学のキャリアセンターや労働基準監督署などに相談することもできます。
結論として、長期インターンそのものがブラックというわけではなく、ブラックな企業が一部存在するだけです。適正なインターンを見極め、健全な環境で実力を伸ばせば、搾取どころか貴重な成長機会になります。「ブラックのリスクが怖い」と諦めるのではなく、本記事末尾のチェックリストなどを参考にホワイトな良質インターン先を選ぶ目を養いましょう。きちんと選べば「インターンして良かった!」と思えるはずです。
◇リモート主体で仲間ができない
よくある声:「最近はリモートOKのインターンも多いけど、家で一人で作業じゃ社員とも他の学生とも仲良くなれないのでは?」
コロナ以降、フルリモートや在宅で参加できる長期インターンも増えました。遠方の学生にもチャンスが広がる一方、「画面越しでは相談しにくい」「雑談がなく孤独」といったデメリットも指摘されています。オフラインでの人間関係が築けないため孤独を感じやすいという声はもっともです。隣にインターン仲間や先輩社員がいない環境では、気軽に質問したり刺激を受けたりする機会が減ってしまいます。また、自宅だと仕事とプライベートの切り分けが難しくダラダラしてしまうという自己管理上の課題もあります。
実際には:しかし、リモートインターンにも工夫次第で仲間はできます。まず、リモートの利点として地方学生でも都会の企業で働ける、忙しい人でも柔軟に参加できるという点が挙げられます。通勤が不要なので授業や部活との両立もしやすく、空いた時間に業務を進められるメリットは大きいです。実際「週5出勤は無理だけどリモートなら参加できた」という学生も多く、そうした人がキャリアを積む機会を得られるのは意義深いでしょう。
仲間作りの工夫:リモートでも積極的にコミュニケーションを図ればチームの一員になれます。例えば、チャットツールで他のインターン生や社員と情報交換したり、毎朝のオンライン朝会で今日の予定を共有するなど、企業側も連帯感を生む施策をとっているところが増えました。また、「リモートだと教育が受けづらい」という課題に対応し、定期的にメンターと1on1ミーティングを設定したり、疑問があればすぐビデオ通話で質問できる体制を整えている企業もあります。オフラインでは得られない全国の優秀な学生との繋がりができる可能性もあります(リモートインターン生同士で自主勉強会を開いた例もあります)。
もちろん、フルリモートではオフライン飲み会のような親睦は図りにくいかもしれません。その場合、ハイブリッド型(基本リモートだが月1回出社日あり等)のインターンを選ぶのも手です。実際、「オンラインで普段働き、月1回の出社日に顔を合わせることでモチベーション維持になった」という声もあります。要はデメリットを理解した上で、自分なりに補完すればよいのです。
自己管理スキル向上:逆に言えば、リモート環境は自分を律する良いトレーニングになります。誰も見ていなくても成果を出す経験は、将来どんな働き方にも通用するでしょう。リモート勤務時は意識的なコミュニケーションが必要ですが、それも社会人スキルの一つです。
結論として、「仲間ができないから意味ない」とリモートインターンを敬遠する必要はありません。孤独感を感じるデメリットはあるものの、その分柔軟性や全国規模での出会いなどメリットもあります。そして何より、自ら積極的に周囲と関わろうとする人には、オンライン上でも必ず手を差し伸べてくれる仲間や先輩がいます。リモートであれ出社型であれ、「学びたい!」という熱意が仲間を呼び寄せることを忘れないでください。
長期インターンがもたらす5つのメリット
5つの疑念にお答えしてきましたが、長期インターンにはそれ以上に多くのメリットがあります。ここでは代表的なメリットを5つ紹介しましょう。長期インターンに参加すると、あなたが得られるものは決して「無意味」どころか、将来につながる大きな財産となります。
◇実務スキル習得
長期インターン最大のメリットは、座学では得られない実務スキルが身につくことです。社員とほぼ同じ環境で長期間業務に携わるため、仕事の一連の流れやPDCAサイクルを体験できます。例えば営業のインターンであればビジネスマナーや資料作成、電話対応、課題ヒアリングから提案まで一通り経験でき、「ビジネスの基礎」が凝縮されています。エンジニア職ならチーム開発のプロセスやコードレビューを通じて、学校の課題では味わえない実践的スキルが習得できるでしょう。実際、ある長期インターン経験者は「学生時代にプログラミングスキルを身につけ、論理的思考力も鍛えられた」と述べています。このように、長期インターンで身につくスキルは無限にあります。さらに、自分が担当した業務を通じて専門知識の深掘りも可能です。マーケティングインターンなら市場分析手法や広告運用ノウハウ、ライターインターンならSEOや企画立案など、各職種のリアルなスキルセットを学生のうちに獲得できます。これら実務スキルは就活時だけでなく、その後のキャリア全般にわたり強力な武器となるでしょう。
◇就活アピール
長期インターンの経験は就職活動における強力なアピールポイントになります。ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)として具体的な成果や成長を語れるからです。例えば「インターンで○○のプロジェクトに携わり、売上△%向上に貢献した」「週2勤務で○社の顧客開拓を任され、計15件の商談を獲得した」といった実績は、面接官の目にも明確なインパクトを与えます。実際、人事担当者の多くは長期インターン経験を高く評価しています。「単に参加しただけでなく、何を学びどう成長したか」が重要であり、それを具体的に語れるならば強力な武器になるのです。さらに前述の通り、データ上も長期インターン経験者の内定率は未経験者より約1.2倍高いという結果が出ています。インターン参加自体があなたの意欲と行動力の証明ですし、得られたスキルや知見は他の就活生との差別化要素になります。要は、インターンを通じて自分が何者になったかを語れるよう準備しておけば、就活では大いに有利に働くでしょう。実務経験を積んでいる分、企業理解や仕事理解も深まっており、志望動機や自己PRにも説得力が増すはずです。
◇キャリア探索
長期インターンは自分のキャリアを探索する絶好の機会でもあります。実際の職場で働くことで、その業界や職種が自分に合っているか肌で感じられるからです。例えば、IT企業でエンジニアインターンをしてみて「ものづくりの楽しさに目覚めた」「逆に自分は開発より企画の方が向いていそうだ」と気付くこともあります。あるいはベンチャー企業のインターンを通じて「将来は大企業よりベンチャー志向だ」と方向性が定まる学生もいます。長期インターン中に業界研究・企業研究を深められるのは大きなメリットです。働いてみて初めて業界の動向や仕事の実態が見えるため、ミスマッチの少ない就職先選びにつながります。実際に「インターン経験のおかげで、本選考での志望業界を変更したが結果的に納得のいく進路になった」というケースもあります。さらに、自身の適性を知る機会にもなります。「毎日違う業務をこなすのは苦手だけどルーティン作業は得意」「人と話す仕事にやりがいを感じた」など、長期インターンを通じて初めて見えてくる自己分析の材料も多いです。これらはその後のキャリア選択において貴重な指針となるでしょう。要するに、長期インターンは将来のキャリア選択の実験の場とも言えます。たとえインターン先に就職しなくても、得た経験によってミスマッチを減らし、自分に合った進路を探るヒントが得られるのです。
◇人脈形成
人脈(ネットワーク)はキャリアにおいて大きな財産です。長期インターンでは、社員や他のインターン生など多くの人とのつながりが生まれます。業務を通じて企業の先輩社員と信頼関係を築ければ、就活時に推薦をもらえたり、働きぶりが評価されてその企業からオファーを受ける可能性もあります。仮にインターン先に就職しなくても、そこで知り合った社会人から業界内の採用情報を紹介してもらえたり、OB訪問的にキャリア相談に乗ってもらえたりといった恩恵があるでしょう。実際、「インターン先の上司が他社を紹介してくれた」「取引先との縁で別の内定に繋がった」という事例もあります。さらに、共に切磋琢磨した他大学のインターン仲間は貴重な同志です。情報交換することで就活へのモチベーションが上がったり、お互いの成長に刺激を与え合うことができます。将来、異なる会社で働くことになっても同期のようなつながりが生きる場面があるかもしれません。長期インターンをきっかけに知り合った仲間と起業したケースすらあります。要は、長期インターンは学生のうちにビジネス人脈を構築できる貴重な場なのです。人脈は就活のみならず社会人生活においてもあなたを支えてくれる財産になりますから、ぜひ積極的に周囲と関係構築してみてください。
◇報酬・経済面
長期インターンの多くは有給であり、働きながら収入を得られる点もメリットです。前述のように時給1,000~1,500円程度が一般的で、週2~3日勤務でも月に数万円の収入になります。これは学生のアルバイトと同程度かそれ以上の収入源になり得ます。特に、長期インターンに参加することでアルバイトのシフトを減らす必要がある場合などは、有給インターンを選ぶことで金銭面の不安を軽減できます。実際に企業の一員として働きお金を稼ぐ経験は、社会人としての意識も高まるでしょう。「成果に対して報酬を得る」ことの重みを学生のうちに体感できるのは貴重です。ある学生は「アルバイトのように時給制ではなく、自分の成果で報酬を得られることに魅力を感じた」とインターン参加の動機を語っています。結果を出せばインセンティブが支給されるインターンもあり、頑張りが収入に直結するやりがいがあります。もちろんお金だけが目的ではありませんが、経済的自立に近づけるという点でも長期インターンは有意義です。交通費支給や社員食堂利用OKなど福利厚生が受けられる場合もあります。要するに、長期インターンは「学び+収入」の両方を得られる一石二鳥の機会です。大学生活で得る経験に加えて社会人としての責任感と経済感覚も身につくため、より実践的なお金の使い方・時間の使い方ができるようになるでしょう。
失敗しないインターン先の選び方
長期インターンを価値あるものにするためには、どんな企業でどんな経験をするかが極めて重要です。「意味ない」時間にしないためにも、インターン先選びで以下のポイントをチェックしましょう。応募前に確認すべき事項をチェックリスト形式でまとめました。
- 業務内容が明示されているか–求人情報や面談時に、インターン生の仕事内容が具体的に説明されているか確認しましょう。ジョブディスクリプションがしっかりしていれば、単なる雑用で終わる可能性は低くなります。逆に「何をするのか曖昧」な募集は要注意です。入ってみたら雑務ばかり…を防ぐため、事前に業務イメージを持てる企業を選んでください。
- OJT体制・メンターの有無–指導担当者(メンター)が付くかどうかは成長速度に直結します。新人研修やOJTが整備されている企業なら、放置されずに済むでしょう。面接で「最初はどのように仕事を教えてもらえますか?」と聞いてみるのも有効です。フィードバックなく放置される環境では成長実感が得られません。メンター制度や定期面談がある企業は安心です。
- 成果物へのフィードバック頻度–どれくらいの頻度でフィードバックをもらえるかも重要です。週次ミーティングや月次レビューがあると、自分の課題を早期に改善できます。何の振り返りもなくやりっぱなしだと、「自分は成長しているのか?」と不安になります。理想は都度フィードバックですが、最低でも月1回は上司やメンターから評価・アドバイスをもらえる環境が望ましいでしょう。
- 有給/無給・交通費支給の条件–報酬条件はしっかり確認しましょう。有給がもちろん望ましいですが、仮に無給の場合でも交通費支給やランチ補助などのケアがあるかチェックしてください。無給長期インターンは基本おすすめできませんが、どうしても志望業界で無給しか募集がない場合は、自分が納得できるか慎重に判断を。少なくとも労働契約書を交わす企業か確認し、違和感があれば遠慮なく質問しましょう。
- 週あたり稼働時間と学業との両立度–求められる出勤日数・時間が自分の学業と両立可能かを検討します。週4~5フルタイムなど過度な条件だと履修に支障が出ます。平均的には週2~3日が多いので、自分の時間割や卒論との兼ね合いを考えて無理のない範囲に収めましょう。試験期間の調整可否も確認ポイントです。「授業優先でOK」「テスト前は勤務ゼロ可」の企業は良心的です。
- 企業文化とパーパス(目的)への共感度–その企業のミッションや事業内容に共感できるかは意外に重要です。自分が興味を持てない業界・商品だとモチベーションが続きません。逆に「このサービスは社会の役に立つ」と思える企業なら主体的に学べます。実際、事業内容に共感して入ったインターン生は長続きする秘訣だと企業側も述べています。エントリー前に企業HPやSNSを見て価値観に共鳴できるかチェックしましょう。
- 長期雇用・内定直結制度の有無–インターンからの社員登用制度や終了後の特別選考枠があるか確認してみましょう。ベンチャー企業などでは「インターン生を優先的に新卒採用する」ケースも増えています。必ずしも内定直結が目的でなくても、そうした制度がある企業はインターン生の成長や貢献を真剣に見てくれる傾向にあります。あなた自身が気に入ればそのまま就職…という選択肢も視野に入ります。
- 既存インターン生の離脱率–可能ならその企業で過去にインターンした学生の様子をリサーチしましょう。離脱率が高かったり短期間で辞める人が続出していれば何か問題があるかもしれません。逆に、「1年以上続くインターン生がいる」「インターン生から社員登用された人がいる」企業は環境が良い証拠です。OB訪問やSNSで体験談を探してみるのも有効です。
- リモート可否・勤務地アクセス–働く場所やスタイルも事前に確認を。リモート希望ならフルリモート可の求人を探す必要がありますし、出社型なら自宅や大学から無理なく通える勤務地かチェックしましょう。リモートの場合、オンラインでのフォロー体制(定期面談やチャットの活発さ)があるか、出社型の場合、職場の雰囲気(インターン生が溶け込みやすいか)なども判断材料です。どちらにせよ、自分に合った働き方かどうかをイメージして選びましょう。
- NDA/インサイダー情報管理体制–インターン生にも秘密保持契約(NDA)を結ばせる企業か確認してみてください。NDAを交わす企業はインターン生に重要なプロジェクトや機密情報を扱わせる意思があるということです。つまり本気で戦力として期待している証とも言えます。情報管理体制がしっかりしている会社はコンプライアンス意識も高く、安心して働けるでしょう。逆に何の取り決めもないまま顧客情報にアクセスさせるような所はリスクがあります。契約周りの丁寧さも見極めましょう。
以上、10項目のチェックリストを紹介しました。インターン先選びの際は「求人情報+面接」でこれらを確認し、自分に合った成長できる環境かを見定めてください。もちろん全てを満たす完璧な案件は少ないかもしれませんが、譲れない条件と妥協点を整理しておくとミスマッチを防げます。このリストを活用し、「失敗しないインターン先選び」の参考にしてください。
体験談インタビュー
実際に長期インターンを経験した学生たちは、どんな悩みを抱え、何を得たのでしょうか。また、受け入れ企業の担当者はインターン生の何を評価しているのでしょうか。ここでは学生2名と企業担当者1名のインタビュー形式で、それぞれのリアルな声をお届けします。成功事例から「意味ない」を乗り越えるヒントを探ってみましょう。
学生Aさん(関西私立大・マーケティング職インターン/参加期間:6ヶ月)
プロフィール:Aさんは東京都内の私立大学に通う3年生。マーケティング系スタートアップで6か月間、長期インターンを経験しました。在学中はキックボクシングの部活と飲食店アルバイトに励んでいましたが、「社会人になる前に仕事を経験し、自分の力で成果を出して報酬を得てみたい」という想いから長期インターンに挑戦しました。
インターン先と業務内容:株式会社X(マーケティング支援のベンチャー)にて、インサイドセールス(内勤営業)の業務を担当。具体的には、中小企業のリストに電話をかけ、自社サービスの案内をして営業アポイントを獲得するという役割でした。週2~3日、一日8時間ほど勤務し、残りの日に授業と部活をこなす生活です。最初は「学生の自分に営業なんて務まるのか?」と不安もありましたが、上司からトークスクリプトを教わり、先輩社員のコールを横で聞く研修からスタート。徐々に一人で電話対応できるようになりました。
感じた壁と乗り越え方:長期インターン開始直後は、部活との両立や慣れない電話営業に苦戦し、「正直きついな…」と思う日もあったそうです。特に何度電話してもうまくアポイントが取れない日は、「1日頑張って成果ゼロだった…自分には向いていないのでは」と落ち込むこともありました。そんなとき、架電が上手な先輩社員がAさんの様子を察して声をかけてくれました。「今日は運が悪かっただけだよ」「こういう切り返しトークを試してみたら?」と具体的なアドバイスと励ましをもらい、メンタル面でも技術面でも支えてもらえたおかげで踏ん張れたといいます。この経験からAさんは、「困ったら素直に頼っていいんだ」と気づき、それ以降は分からないことを放置せずすぐ質問するよう心がけました。まさに長期インターンを通じて自分から積極的に学びに行く姿勢が身についたと語っています。
成果と成長:目標としていた「1日3件アポ取得」を達成するため、先輩の話し方を徹底的に真似たり、自社サービスの強みを明確に伝えられるよう練習した結果、後半には安定して目標をクリアできるようになりました。それに伴い、成果に応じたインセンティブ報酬も獲得し、自分の頑張りが数字と収入に表れる喜びを味わいました。「自分の成長を感じた瞬間や、成果を出してボーナスをもらえた瞬間はやりがいを感じました!」と振り返っています。また、社内の長期インターン仲間や社員との距離が近く、手厚いサポートを受けながら成長できる環境自体にも大きなやりがいを感じたそうです。6か月を終えた頃には、初めは苦手意識のあった「人に頼る・質問する」ことの大切さを実感し、「怖がらずにフィードバックを求めることでどんどん学べる」と考え方が変わったと言います。
担当社員のコメント:Aさんの上司だったYさんは、「彼女は非常に真面目で最初は遠慮がちでしたが、こちらがフィードバックすると素直に吸収しどんどん成長しました」と評価しています。最初の頃は電話で断られるたび落ち込んでいたAさんが、自分から積極的に「この言い方どう思いますか?」と尋ねてくるようになり、後半は新人アルバイトにアドバイスできるほど頼もしく成長したそうです。Yさん曰く、「長期インターンは受け身だと意味がないけど、Aさんのように目的意識を持って挑戦すれば大学生活では得られない飛躍ができる」とのことでした。Aさんはインターン終了後、無事志望業界の大手企業から内定を獲得し、「インターンでの営業経験が面接で高く評価された」と喜んでいます。「つらい瞬間もあったけど、“意味を生み出す”努力をしたからこそ今の自分がある」と笑顔で語ってくれました。
関西国立大・エンジニア職インターン/参加期間:1年
プロフィール:Bさんは地方の国立大学に通う大学院生。情報系専攻で、在学中に東京のスタートアップ企業でフルリモートのエンジニア長期インターンを1年間経験しました。地元ではエンジニアの実践機会が少なく、「遠隔でも都会の開発現場に関わりたい」と思ったのが参加の動機です。
インターン先と業務内容:株式会社Z(Webサービス開発企業)の開発チームにジョインし、Pythonを用いたデータ分析ツールの開発補助を担当しました。週約15~20時間を自宅から在宅勤務し、タスク管理はオンラインツールで行います。最初は先輩エンジニアの指示のもと簡単なバグ修正やテスト業務から始め、徐々に機能追加などコアな部分も任されるようになりました。コードはGitHubで共有し、メンターがコードレビューをしてくれる体制です。
感じた壁と乗り越え方:フルリモートゆえに最初は孤独感との戦いでした。画面越しでは質問タイミングが掴みにくく、エラーで行き詰まっても誰にもすぐ聞けず焦ることがあったそうです。「深夜に一人でデバッグしていて、『自分は何をやっているんだろう…』と不安になった日もありました(笑)」とBさん。しかし途中から、毎朝10分のオンライン朝会で進捗と悩みを共有する仕組みを自ら提案。【毎日状況を報告し、詰まったらすぐチャットやビデオ通話で助けを求める】ようにしたところ、困ったときにすぐ相談できる環境が整いました。「先輩方も“わからないことはすぐ聞いて!”と言ってくれて、遠慮なく頼れるようになった」と言います。加えて、夏休みには思い切って東京のオフィスに数日間訪問。チームのメンバーと直接顔を合わせ交流したことで、一気に親近感が湧き、その後のオンライン業務も格段にやりやすくなりました。「やっぱり一度リアルで会うと違いますね。リモートでも自分はチームの一員だと思えるようになり、孤独感は消えました」と語っています。
成果と成長:1年間のインターンを通じて、Bさんは小さな機能ではありますが一つのプロダクト機能をゼロからリリースまで担当しました。自分が実装を任された検索アルゴリズムの改善で、サービスのデータ処理速度が30%向上する成果を出し、社内でも称賛されました。「学生の書いたコードが本番プロダクトに採用され、多くのユーザーに使われているのを見たときの感動は忘れられません」と言います。また、自己管理能力と主体性が飛躍的に伸びたとも感じています。リモート環境ではサボろうと思えばいくらでもサボれますが、逆に自分を律して成果を出す習慣が身についたとのこと。「研究との両立で時間管理がシビアでしたが、そのおかげで生活にもメリハリがつきました」。さらに「わからないことは素直に質問する」姿勢や、「進んで情報共有するコミュニケーション力」も養われました。これは将来リモートワークが増えても役立つ能力であり、Bさん自身「リモートで成果を出せた経験は今後どんな働き方にも自信になる」と話しています。
担当社員のコメント:Z社でBさんの指導を担当したCTOのM氏は、「最初は黙々と一人で頑張りすぎてしまう印象だったが、次第にチームに働きかける積極性が出てきた」と振り返ります。朝会の提案もBさんからで、「おかげでチーム全員の生産性が上がった」と高く評価しています。M氏は「リモートだからと言って仲間ができないわけではなく、Bさんのように主体的にコミュニケーションをとればしっかり組織に馴染める。彼はまさにそれを体現してくれた」と称賛。最終的にBさんには「ぜひ卒業後もうちで一緒に働かないか」と内定オファーを出したとのことです。M氏は「長期インターンは会社にとっても有益。学生の新鮮な視点が刺激になるし、優秀な人材を早期に見極められる」とも語っていました。Bさん自身、「最初はやめとけば良かったかもと思った瞬間もあったけど(笑)、乗り越えてみれば得るものだらけでした」と笑顔で締めくくりました。
受け入れ企業X社(インターン担当者インタビュー)
プロフィール:X社は都内のIT企業。2018年より長期インターンの受け入れを本格的に開始し、これまでに20名以上の学生を指導してきました。人事責任者のSさんに、企業側から見たインターン生の価値と評価ポイントを伺いました。
インターン受け入れの背景と効果:Sさんによれば、当初は「学生に戦力になる仕事が任せられるのか」「途中で辞めてしまわないか」など不安もあったそうです。しかし蓋を開けてみると、大学卒業や就活時期と重なるケースを除いて多くのインターン生が長く続けてくれており、1年以上継続する学生もいて非常に助かっているとのことでした。実際、あるインターン生は大学院進学までの2年間在籍し、プロジェクトリーダーを任されるまでに成長したそうです。「当初の懸念は杞憂でしたね」とSさん。さらに、インターン制度を始めて1年経つ頃には「インターン生が活躍している」という評判がグループ会社にも広がったといいます。インターン生の存在が社内にも良い刺激を与え、若手社員の指導力向上や組織の活性化にもつながったそうです。「学生さんのフレッシュな視点での提案はハッとさせられるものがあります。社内のマンネリ化した空気を変える効果も大きいです」とSさんは実感を語ります。
企業が評価するポイント:ズバリ、「主体性と吸収力」が最も重視されるとのこと。Sさんは「スキルは入社後でも身につきますが、主体的に動けるかどうかはその人の姿勢です。長期インターンでは特に“自ら学ぼうとする意欲”を見ています」と明言されました。例えばX社ではインターン面接で「最近自分から挑戦したこと」を必ず尋ね、受け身ではない人材か見極めるそうです。実際、これまで採用したインターン生は皆さんチャレンジ精神旺盛で、「言われたことだけでなく+αの提案をしてくれる人ばかりだった」といいます。もう一点、「会社のミッション・バリューへの共感」も重視ポイントです。「どんなに優秀でも自社の理念に共感していないと長続きしません。逆に共感して入ってきてくれたインターン生は長く続いて成果も出してくれる傾向があります」とのことでした。インターン選考でも応募者の志望動機や価値観をしっかり確認するようにしているそうです。
インターン生へのメッセージ:最後にSさんに「学生へのアドバイス」を伺うと、「就活のためだけにインターンをしないでほしい」と強調されました。「もちろん就活に有利になる側面はありますが、それ以上にインターンは社会人視点を持つチャンスです。目先の内定だけでなく、その後のキャリア基盤づくりだと思って取り組んでほしいですね」。また、「長期インターンは意味があるかないか、自分次第です。せっかく参加するなら目標を決めて主体的に動き、たくさん失敗と成長を経験してください」とも。Sさんの会社では、インターン生一人ひとりに最初に「このインターンで成し遂げたい目標」を書いてもらい、定期的に見直す取り組みをしているそうです。「与えられるのを待つのではなく、自分で意味を作りにいく姿勢が大事。私たち企業側も全力でサポートしますので、お互いに実りある時間にしましょう」という力強いメッセージをいただきました。
受け入れ企業の視点からも、「長期インターンは学生・企業双方にメリットが大きい」ことが改めて分かります。適切な努力をすれば、企業もそれに応えてくれるという好循環が生まれるでしょう。
まとめ
長期インターンは決して「意味ない」どころか、学生生活を飛躍させる貴重な機会です。本記事で見てきた通り、
- 「意味ない」と言われる理由は誤解や準備不足によるものであり、正しい目的意識と行動で大きな価値を得られる
- 実践的なスキル習得や人脈形成など、長期インターンならではのメリットが数多く存在する。
- 失敗しないためのポイントを押さえてインターン先を選べば、学業と両立しつつ将来に繋がる経験ができる。
長期インターンはあなたの可能性を大きく広げてくれるはずです。再検索する前にこのページをブックマークし、いつでもポイントを確認しながら実践に移しましょう。「意味ある」インターン経験を積んで、あなたの未来に活かしてください!
インターン.comは大手の求人も豊富に掲載!
大阪で長期インターンシップを検討している方は、インターン.comをご利用ください。長期のインターン に特化しており、大手の求人も豊富に掲載しています。自身の適性や目標に合ったインターンシップを見 つけられるよう、カジュアル面談を無料で行っており、キャリアアドバイザーがインターンシップに関す るお悩み・ご相談に対応いたします。ぜひ、ご予約ください。
カジュアル面談予約はこちら